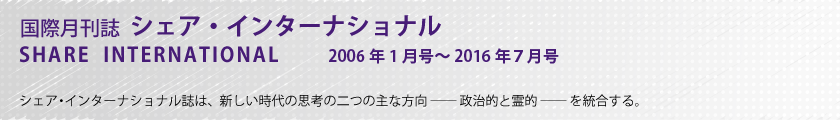緊縮経済と似非(えせ)理論
パトリシア・ピッチョン
有効ではない経済概念や、科学哲学者が愛する十分な根拠に基づいた理論、つまり説明能力と予測能力の両方を持つ理論という必要不可欠なテストに落第した経済理論に、私たちは催眠術をかけられているのかもしれない。私たちはさらに、その理論に由来し大きな苦しみを引き起こす政策的処方に耐えているのかもしれない。
2008年の経済恐慌後の欧米指導者による初期対応が多かれ少なかれケインズ主義的なやり方を追求するものであったため、これはますます明らかになってきている。経済学者ジョン・メイナード・ケインズは、不景気の時には政府が支出し、豊かな時代には貯蓄することが必要であるという見解を持っていた。2008年には、様々な政府が1930年代の教訓を学んだように思えた。当時は、大恐慌の後の金融引き締めが何百万もの人々の苦難を不必要に増大させたからである。
2008年にアメリカとヨーロッパの数カ国では、極度に複雑な金融「商品」の開発を許していた多くの破産銀行が「量的緩和」政策によって救済された。こうした商品は、安全性と危険性が一緒に束ねられていることを考慮しなかった格付け機関によって高く評価されていた。信用の喪失とその後の経済恐慌によってその商品の高いリスクと低い価値が明らかになったとき、熱心に購入した投資家は数えきれない膨大な資産を失った。同様に明らかになったのは、格付け機関の不穏当な熱意、銀行の無謀さ、適切な監視の不足であった。そのうえ多くの国々には、やがては破裂する持続不可能な不動産バブルがあった。向こう見ずな投機家と、大衆をよりよく守ることができるよう投機活動とこうした活動に巻き込まれたくない人々の預金とを切り離したい人々との間で亀裂が拡大した。これまでのところ、どのような改革がどの程度必要とされるかについてのこの意見の二分化は解消されていない。投機に関与することによる興奮への絶え間ない執着は、何百万もの人々の日々の苦闘から不思議にもかけ離れた金融文化において定着した特徴となったように思える、顧客の福祉への無頓着や無視と組み合わさっている。
もっと奇妙なことに、現在の新古典派の経済理論と経済実態との間で深刻な不釣り合いがあるということがますます明らかになってきている。この不釣り合いはジョーン・ウィークス著『1%のための経済学』にある特定の分析において明白である。この本は、新自由主義の経済的立場の見せかけをはぎ取る、不遜で辛辣な本である。こうした経済的立場は、それが擁護する理論を通して、強力な金融機関、シンクタンク、一部の政党、強力なビジネスマン、多くの学者、幅広い出版物などによってしばしば表現される。このことは重要である。この立場から生じる政策によって途方もない損害が生じる可能性もあるからである。
ここに幾つかの例がある。
ウィークス氏によると、新古典派の経済理論は政府を本質的に「お荷物」として見る。これは、人間社会は自らがつくった機関に自発的に加わったり離れたりする「個人」から構成されているという自己中心的な世界観と関連している。さらに、市場は政府から分離した領域と見なされ、このことから当然、政府は市場に干渉するということになる。しかしウィークス氏は、(生産と売買の複雑な過程である)市場は政府を「その持続的な機能の必要条件としてだけでなく、その存在の前提条件として」必要とすると指摘する。政府の規制のおかげで市場は機能する。したがって、政府の機能を縮小し過ぎるべきではない。金融機関が監視を必要とすることも明らかであるからである。
もう一つの異論の多い問題は、いわゆる自由貿易である。これは、裕福な人々を自由に利するという意味でのみ自由なものである。世界中で貿易自由化を確実にすることにより、そのような「開かれた」「地球規模の」競争のもとで労働者がさらに大きな圧力にさらされ、世界中の労働者と競わなければならなくなる。実際、その擁護者たちにとって「自由」とは本当のところ、政府の「干渉」によって束縛されない貿易を意味する。労働者は、結果として恒久的な賃金抑制に相応するものを受け入れることを強いられる。大陸にまたがる貿易は主に企業によって行われ、その企業は主に企業同士で貿易を行う。それぞれの国で労働者に(どうしようもないほどわずかな最低賃金ではなく)少なくとも生活するための賃金が支払われるよう、各国政府が規制を設けるために結束するならば、企業は(おそらく抗議するかもしれないが)適応することになるだろう。
この規制されない環境の中でアメリカの労働者の実際の購買力がこの40年以上にわたって増加していないのは、おそらく偶然ではないだろう。しかも、賃金が停滞し、減少し、支払われないことさえある状態は今や、開発途上世界だけでなく、ヨーロッパの何百万もの人々の運命となっている。世界の多くの地域での労働者の貧困化は、全く進歩などではない。
最後の例となるが、2010年2月にアメリカとヨーロッパの数カ国がG7財務担当大臣会議で再び緊縮政策を支持したことが明らかになった。これが間違った方向であったことは今や明白である。問題になっている経済は、大部分において十分に強くはないからである。いまだに膨大な民間の負債があり、失業や多くの低賃金雇用がある。
ジョーン・ウィークス氏は著書の最終章で、緊縮経済の代替策を提案している。彼は貧困の緩和と貧困の削減との間の重要な区別をしている。戦後(1945年~1970年)、西欧諸国とアメリカで実行された完全雇用という目標は、共和党政権と民主党政権の両方によって、あるいはイギリスにおいては保守党政権と労働党政権の両方によって支持されたということを知り、驚く人もいるかもしれない。公的部門は、完全雇用を維持することに責任を負う社会機関として機能すべきである、とウィークス氏は主張している。それには革新は全く必要とされない。「現実的な最低水準まで失業を減らすほどの総支出レベルを達成するために」支出を増加させることができる。そして経済が回復すると、公共部門は「民間部門の増加に合わせるためにその支出規模を縮小することができる」。
技術的には単純で容易に実施できるこの包括案は実際に戦後の数十年間に実行された、とウィークス氏は指摘している。1970年代以降、こうした政策がなくなっていったのは、政府が完全雇用に対する責任を放棄したからであり、その実施がより困難になったからでも、その必要性が低下したからでもない。21世紀において、大多数の人々の現実の生活に対処しようとする決断は、私たちの経済をより再分配的なものにする政策変化を可能にし得る。そしてこれが、1%よりもむしろ99%の人々の必要を満たすことが意味することの重要な部分なのである。
参照文献:
John F. Weeks, Economics of the 1%: How Mainstream Economics Serves the Rich, Obscures Reality and Distorts Policy(Anthem Press, London, 2014); Ann Pettifor and Douglas Coe, The IMF and the end of austerity; primeeconomics.org(October 2012); Paul Krugman, How the Case for Austerity Has Crumbled(The New York Review of Books, June 2013); Nina Shapiro, Keynes, Steindl, and the Critique of Austerity Economics (Monthly Review Volume 64, Number 3, 2012); Global Growth Disappoints, Pace of Recovery Uneven and Country-Specific (IMF Survey Magazine, October 2014)