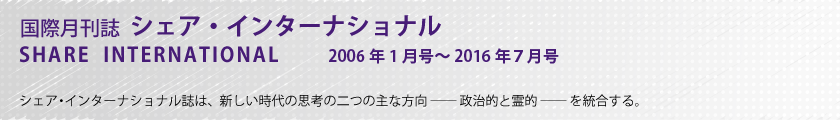臨死体験に関する研究
パトリシア・ピッチョン
「……死は、経験を着実に積み上げていく人生の序章でしかない……それは一つの意識状態から別の意識状態への明確な移行を印すものである」
「……死を形態のイリュージョンから私たちを自由にする経験と見なすのが最もよいであろう……」
(『死──大いなる冒険』の序章で引用されたアリス・
ベイリー『ベツレヘムからカルバリーへ』の文章)
臨死体験に関する何十年にも及ぶ研究には、臨床的に死を宣告されたが、別の次元へと旅し、すでに亡くなった愛する人々との接触からの慰めや、きわめて純粋な愛を示した存在からの知恵を得たように思える人々による何千件もの本人の報告が含まれている。最も重要なことは、現代医療の蘇生技術の向上のおかげで生き延びた多くの人々が、そのような体験の後で死の恐怖をなくしたと報告していることである。そのような人々の体験は、偉大な霊的覚者の見解と一致するところが多いが、現代の多くの科学者が抱く現在の物質主義的な枠組みとはあまり一致しないようである。チベット人のジュワル・クール覚者と密接に働いたアリス・ベイリーの言葉を借りれば、「死とは、本質的に意識の問題である。私たちはある瞬間、物質界上で意識しているが、次の瞬間には、別の界層へと撤退し、そこで活発に意識しているということである」。(『死──大いなる冒険』第Ⅱ部)
人が心停止などの何らか重症に陥り、心拍がなく、脳が停止した、つまり脳波計が「フラット」になったように思えるとき、その人は通常、臨床的に死亡したと見なされる。しかし、多くの最近の研究は、数多くの事例の一部である以下の事例のように、肉体とは別に意識が存続することを示しているようである。
深刻な心臓病をかかえた男性が瀕死の状態にあり、別の病棟にいた彼の姉は糖尿病性昏睡に陥っていた。男性は自分の肉体を離れ、医療関係者が彼を蘇生させようとしているのを見て、それから突然気がつくと、何が起こっているのかについて姉と話していた。彼女はその後、彼から遠ざかっていき、トンネルの向こうに行ってしまうのを彼は見た。目覚めたとき、彼は医師に、自分の姉が亡くなったと言った。医師は最初否定したが、看護師は彼女が亡くなったことを確認した。(レイモンド・ムーディ『光の彼方に』)
多くの人がトンネルを通り、それから美しくまばゆい光の中に入っていったと報告している。それからしばしば、先立った親族に会い、美しい牧場や言い表せないほど生き生きとした色彩の花々を目にし、そして、たぐいまれな無条件の愛が彼らを取り巻く。この段階において「光の存在」がよく現れ、テレパシーで意思を伝える。生涯の主な出来事が走馬灯のように駆け巡るのを見たと多くの人が報告している。自分がいかに他の人を傷つけたかが分かり、自分の間違った行いが引き起こした感情を感じ取ることができる。この過程の間に自分を裁くことができるのはまさしく、映画のように「見る」ことができるだけでなく、自分がしたことを感じることができるからであり、これが彼らの後悔の念の土台となる。「光の存在」(それを神やイエスと呼ぶ人もいれば、もし宗教を信じていなければ、無条件の愛をもった存在と描写する人もいる)は導き、すべてを受け入れる愛と光でその人を包み込む。一部の記述では、この愛と光は、互換性のあるものだとされているようである。
当事者はある時点で、しばしば境界に気づき、それを越えれば戻って来ることができないことを知る。その境界の向こうのことを素晴らしい光の街と呼ぶ人もいる。「ある街が見えました。……建物がありました。……ぴかぴかと光り輝いていました。そこにいる人々は幸せそうでした。きらめく水、泉がありました。……光の街という言い方がふさわしいと思います。……素晴らしいものでした。……しかし、ここに入っていれば、二度と戻ってくることはなかっただろうと思います」(レイモンド・ムーディ『かいまみた死後の世界』)。人々はしばしば戻りたいと思わないが、「子供たちがあなたを必要としている」とか「あなたにはまだやるべきことがある」というような言葉で、戻るように勧められることがある。
人生に戻ると、どういうわけか深刻な状態が癒される人もいる。多くの人は、人生の目的について新たな感覚を抱くようになったと、あるいは、完全に新しい感覚を抱くようになったとさえ語る。過去数十年間の多くの研究は、こうした体験の特徴の一部または全部を記録し、こうした「臨死体験」つまりNDE(初期の研究者、精神科医であり、『光の彼方に』などの先駆的な研究書の著者であるレイモンド・ムーディ博士の造語)のパターンを明らかにしている。異文化に共通のパターンが存在することも明らかにされてきた。(ジェフリー・ロング博士とポール・ペリーの共著『死後の生命の証拠』を参照)
大人はまた、子供時代の生き生きとしたNDEを大人になっても覚えている。ケイティと呼ばれる女性は、3歳の時に喉にものを詰まらせて気絶し、消防士であった彼女の祖父も彼女を生き返らせることはできなかった。彼女は肉体を去り、別の部屋の輝かしい光の方に移動した。ある存在が彼女を包み込み、その存在は「信じられないほどの平安、愛、受容、静けさ、喜びでした」と彼女は述べている。こう書くとすぐに、当時の感情に引き戻され、「私はいまだに嬉しくなります」と彼女は付け加えている。当時はあまりに幼くて神という概念が理解できなかったため、この存在を神としては体験しなかったが、「私はこの存在を、今の私にしてくれたものとして実際に体験しました」。(『死後の生命の証拠』)
ある脳神経外科医の説明
アメリカ人の脳神経外科医エベン・アレグザンダー博士は、生き返った患者が彼に告げようとした興味深い体験に耳を貸そうとしなかった。彼は自分のことを「実践を通して学ぶタイプ」と描写し、自分が感じたり触ったりできないものになかなか関心を持つことがなかった。彼は科学の「明朗性」を愛した。彼によると、頭痛と意識低下を患っていた患者が磁気共鳴画像装置(MRI)検査を受けると、脳腫瘍が見つかった。患者は手術を受け、脳腫瘍は除去され、症状はなくなった。アレグザンダー博士はまた、顕微鏡を通してニューロン(神経細胞)を見たとき、脳がどのようにして意識を生じさせるのかを科学は発見していないことを知った。しかし、科学がいつの日にかその答えを見いだすことを彼は確信していた。マインド(心)は脳の高度な働きにすぎないという物質主義的な見方を完全に支持していたのである。しかし、珍しい種類の細菌性髄膜炎にかかって1週間昏睡状態にあったとき、彼は尋常でない旅に出て、そこで美しい少女の形態をとったある「存在」と接触した。彼女はただ彼に、(言葉を使わないで)彼が愛され慈しまれていることを告げた。愛が「あるゆることの基本」であるということ、愛は理解するのが難しい抽象的な概念ではなく、妬みや利己的感情のない、力強くて純粋で無条件のものであることを彼は認識した。彼はまた神聖な存在と出会った。何となく「神の存在はきわめて間近に感じられ、自分との間に全く距離がないように思えた」。(『プルーフ・オブ・ヘブン』)
アレグザンダー博士の多くの質問に答えたこの存在は、その広大さにもかかわらず、「温かく」、「親身」であった。「私はその場所で、無数の宇宙に豊かな生命が息づいているのを見た。その中には人類よりはるかに進歩した知性を備えるものたちもいた」。彼は「数限りない高次の次元」があることも知った。それは、その中に入り、直接体験するかたちでしか知る方法がない次元である(『プルーフ・オブ・ヘブン』)。この存在状態における知識は、記憶する必要のない直接の洞察として得られ、直接蓄えられ、明瞭に覚えているものであることを彼は認めている。
生存者の生活はどのように変わるか
多くのNDEの生存者は、死の恐怖をなくすだけでなく、「人生の振り返り」を体験するため、特に他者のことをもっと気づかうという意味において「もっとよくやろう」という決意につながるようである。ロシア出身のビクトルは全く宗教的な背景を持たず、鬱病を患い、自分の研究を終えることについて心配していた。彼の人生は無意味なように思えた。それから、NDEの間、彼は尋常でない光に包まれた。その光の中には愛と平安があり、完全に安全であるように感じられた。「私が歩まなければならない新しい道が見えない力によって開かれました。それは、私がそのために努力していくべきものでした。私の人生は無駄ではなかったということ」、「自分の必要だけでなく周りの人の必要を満たす」ような目標を持つべきであるということ、毎日が「意味のある良い活動に満ちているべきだ」ということを彼は知った。トルコ出身のグルデンは、NDEの後、より大きな喜びをもって人々と会い、怒ることはほとんどなくなったと語っている。「私の日常は愛に満たされ、平和です。私は見知らぬ人々を助けることに喜びを感じます」。インド出身のスレシュは、「神は愛、光、動きでした」と、そして神を受け入れるためには、かつて言い争いをしたすべての人に、また「私がそうと知りながら、あるいは知らないうちに苦痛を与えたすべての人」に謝ることによって、ハートとマインドを清めなければならないと述べた。自分が経験した愛は「言葉では表現できないものだ」と彼は付け加えた。
ベンジャミン・クレームの師は次のように書いている。
「来るべき宝瓶宮(アクエリアス)の周期には、再生誕の法則に関して全く新しいアプローチが取られるだろう。……人間自身が思考と行動を通して自分の生活環境をつくることを知るようになるだろう。そしてまたこの同じ法則の働きによって、人間の性質や状態をより良い方向に変えることができることを知るだろう。
これが人生の意味と目的を再評価することにつながり、死の事実についてより健全なアプローチが生まれるだろう。すべての生命──生まれていようがいまいが──の連続性に関する理解が、今日の恐怖に取って代わるだろう。死がすべての終わりという古い恐怖症は、人間の心(マインド)を照らす新しい光の中に消え去るだろう。迷信や無知の暗黒の隅々にこの新しい光が輝き、永遠なる魂としての人間の神性を目覚めさせるだろう」
(『覚者は語る』「再生誕の法則」1985年1月号)
(ジェフリー・ロング博士による興味深い異文化研究を
引用したスティーブ・ミラー『臨死体験』102~103頁と、www.nderf.orgを参照)
参考文献:
Death: The Great Adventure(死──大いなる冒険), Lucis Press Ltd, London, 1990. アリス・ベイリーとチベット人の覚者ジュワル・クールの著作を2人の秘教徒が編纂したもの。
エベン・アレグザンダー著、白川貴子訳『プルーフ・オブ・ヘブン──脳神経外科医が見た死後の世界』早川書房、2013年。
Jeffrey Long, MD and Paul Perry, Evidence of the Afterlife; The Science of Near-Death Experiences(死後の生命の証拠──臨死体験の科学). HarperOne, New York, 2011; and Jeffrey Long, www.nderfg.org
レイモンド・ムーディ著、中山善之訳『かいまみた死後の世界』評論社、1989年。
レイモンド・ムーディ著、笠原敏雄・河口慶子訳『光の彼方に──死後の世界を垣間みた人々』TBSブリタニカ、1990年。
J.Steve Miller, Near-Death Experiences(臨死体験).Wisdom Creek Press, Acworth, Georgia, 2012。